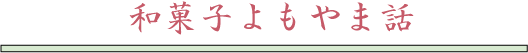
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2011年 9月 初雁
茶道具の香合の中に「二季鳥」というのがあります。 秋に渡来し春にこの地を離れる「雁」を表した香合です。 季節を告げる渡り鳥ですね。 四季の移り変わりを伝える大事な役目を担っていたのでしょう。 しかし、「雁」と言えば、やはり秋! 季語に『初雁』があり、「雁に月」の図があり、「雁来月」とは旧暦の8月のことですね。
 和菓子にも『初雁』の銘を持つものが沢山あります。 茶席で用いる主菓子にはどこのお店も“百合根”と“黒糖”を使って“葛”で仕立てているように思います。 黒糖で練った葛に百合根を加え丸く取っただけのもの。 黒糖風味の葛焼きの中に百合根を加えたもの。 白餡に百合根を加えて中餡とし、黒糖風味の葛皮で覆ったもの。 表現された形は様々ですが、ともかく「雁」の飛ぶ姿=羽を広げた姿を“百合根”のカーブで表しているのです。 黒糖はさしずめ夕闇や夜の暗さの現れでしょうか…。
和菓子にも『初雁』の銘を持つものが沢山あります。 茶席で用いる主菓子にはどこのお店も“百合根”と“黒糖”を使って“葛”で仕立てているように思います。 黒糖で練った葛に百合根を加え丸く取っただけのもの。 黒糖風味の葛焼きの中に百合根を加えたもの。 白餡に百合根を加えて中餡とし、黒糖風味の葛皮で覆ったもの。 表現された形は様々ですが、ともかく「雁」の飛ぶ姿=羽を広げた姿を“百合根”のカーブで表しているのです。 黒糖はさしずめ夕闇や夜の暗さの現れでしょうか…。
私も、この『初雁」を色んな形で作り、教室のレシピにも加えていますが… 今一つ納得出来ていません。 まずは“百合根”が広げた羽に見えない事です。(苦笑) “百合根”が手に入らなかったり、あっても、まだ小さくて…、きっと時期的にはもう少し遅いものだろうなぁ〜?と思います。 おそらくは初物の“百合根”とその年に初めて見る「雁」を喜ぶお菓子なのでしょうね。 「雁渡し」とは旧暦の9月に吹く風のことだそうですから、日本は陰暦で暮らす方がピタッと来るのかも知れませんね。
東京の生徒さんから川越市の『初雁城』という落雁や『初雁焼き』というお芋の形そのままの薄焼煎餅や『初雁糖』という芋納豆などなどを頂きました。 これらはいずれも「雁」を黒胡麻で表現していました。 太田道灌によって建造されたという川越城が“初雁城”と呼ばれていたことに因むものですね。 川越城が完成したのは初秋のことで、築城の祝いの折に頭上を初雁の列が飛んだことからその名がついたのだそうです。