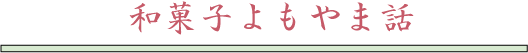
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2011年 10月 山づと
「山づと?」 「そう… 『山づと』と言います。 山の幸、里山からのお土産という意味です。」 お稽古に『山づと』を使うと生徒さんとの間に、必ずこうしたやり取りが生まれます。 『山づと』の“づと”は“苞”の字を当て“包む”という意味です。 お菓子の銘には最近では使われない言葉が用いられることが多々あり、『山づと』もその一つかと思います。
『山づと』は大概「栗」を使ったお菓子で…
 よく目にするのは栗を包み込んだ小豆の漉し餡を棒状の芯にして、周囲を薯蕷の皮で巻いた棹物ですね。
それを2~3㎝の小口に切り、切り口を上に見せたお菓子です。 職人さんとしては当然なのでしょうが、どうすればあのように等しく断面に栗が出せるのか?と、いつも感心します。 我々素人が作ると… 栗と餡の間にでさえ空気が入ってしまって… 切ると形が崩れそうです。 時に“まぐれ”で驚くほど上手く出来ることがあるのですが、何とも、その成功
の秘訣、要領が未だに得られません。 (苦笑)
よく目にするのは栗を包み込んだ小豆の漉し餡を棒状の芯にして、周囲を薯蕷の皮で巻いた棹物ですね。
それを2~3㎝の小口に切り、切り口を上に見せたお菓子です。 職人さんとしては当然なのでしょうが、どうすればあのように等しく断面に栗が出せるのか?と、いつも感心します。 我々素人が作ると… 栗と餡の間にでさえ空気が入ってしまって… 切ると形が崩れそうです。 時に“まぐれ”で驚くほど上手く出来ることがあるのですが、何とも、その成功
の秘訣、要領が未だに得られません。 (苦笑)
 あるいは「こなし生地」で作ったリアルな栗もありますね。 栗そのものや栗の餡を中に包んで栗を形作り、底の部分にケシの実などを付けたものです。 私の教室では、こちらは『山路』という銘で作ります。
あるいは「こなし生地」で作ったリアルな栗もありますね。 栗そのものや栗の餡を中に包んで栗を形作り、底の部分にケシの実などを付けたものです。 私の教室では、こちらは『山路』という銘で作ります。
そして私達が好きな『山づと』に亀屋吉永さんのものがあります。 栗が背負い籠にぎっしり詰まった、まさに『山づと』です。 思うに、このお菓子は桃山生地を小豆の漉し餡で作り、表面に卵を塗って焼いたものではないかと…。 この 、栗 に色艶までをそのまま写した形と大きさ、それを 小さな背負い籠にいっぱいに詰める!という包装の発想が、実に洒落ていて面白いです。


毎年、この季節になると『山づと』を自分のものとしてレシピを完成させたいと思うのですが…、残念ながら大きな宿題を抱えたままで過ごしています。(苦笑)