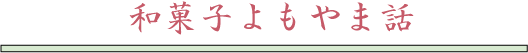
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2010年 5月 初かつお
「目には青葉、山ほととぎす、初鰹」 初夏を愛でるもの…江戸時代の山口素堂という人の句だそうですが、思えば視覚、聴覚、味覚の季語を3つつないだだけ…みたいな面白い句ですよね。
 この句を耳にすると…魚の「鰹」は勿論ですが、つい、美濃忠さんの有名な棹物「初かつお」を思い出します。
お菓子の表面に魚の切り身にみられるような筋模様があり、鰹というよりは「鮪のサク」のような印象です。 それを包丁ではなく糸で切ると切り口が微妙に波打って、さらに魚の切り身のように見えるから不思議です。 色は淡いピンクで、こちらも
当然、実際の鰹とは異なり実に上品な色です。 和菓子の棹物に「かつお」を思いつかれた職人さんの遊び心が素晴らしいと思います。
この句を耳にすると…魚の「鰹」は勿論ですが、つい、美濃忠さんの有名な棹物「初かつお」を思い出します。
お菓子の表面に魚の切り身にみられるような筋模様があり、鰹というよりは「鮪のサク」のような印象です。 それを包丁ではなく糸で切ると切り口が微妙に波打って、さらに魚の切り身のように見えるから不思議です。 色は淡いピンクで、こちらも
当然、実際の鰹とは異なり実に上品な色です。 和菓子の棹物に「かつお」を思いつかれた職人さんの遊び心が素晴らしいと思います。
最初に頂いた時は美濃忠さんが名古屋であることから、「なぁ〜んだぁ。 外郎かぁ〜」と生意気な事を思ったのですが、その食感は私の大好きな「葛外郎」です。 つまり、米粉だけではなく、小麦粉 や葛を含んだ複雑な配合の「外郎」です。 口当たりが柔らかく上品で、あっさり感じます。
外郎といえば子供の頃は「白、黒、抹茶、小豆(あがり)、コーヒー、柚子、さくら♪」のCMでお馴染みの「青柳ういろう」を良く頂きました。 新幹線の車内販売でも アイスクリームや安倍川餅と共に父によくねだった記憶があります。 大人になってからは、美濃忠さんの「初かつお」や山口の豆子郎さんの小ぶりでトロンとした味わいの 「蕨外郎」のファンに…。 神戸にも「長田のういろ」という有名な外郎があるんですよ! 青柳さんのものに近い?といいますか、米粉独特のサクッとした食感のものです。 祖父の好物で… 時折、お土産に買って来てくれた事を思い出します。
そもそも「外郎」とは 穀類の粉に砂糖と水を加えて練り合わせ、蒸して仕上げるお菓子の事です。 その穀類が米粉であったり小麦粉であったり、葛や蕨や片栗を用いたり、それら数種をブレンドしたり…、あるいは餡を混ぜたり…。 その配合によって生地の固さや食感が異なるため、教室では「棹物」「包み(細工)物」「挟み物」に分けて配合を変えています。
今や「外郎と言えば名古屋」ですが、発祥は小田原だとされています。 外郎とは本来「仁丹」に似たお薬で、その口直しに添えられたお菓子が同様に「外郎」と呼ばれるようになった、と言うのが定説です。 そして、そのお薬の外郎は歌舞伎の「外郎売り」でもお分かりのように全国を行脚する薬屋さんによって日本中に広がりました。 同時に各地にお菓子の「外郎」も伝わり、それぞれ特徴のある外郎が生まれた訳ですね。。。