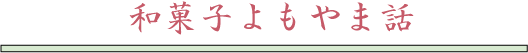
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2010年 4月 落雁(打ち物)
一口に「干菓子」というとその括りは大きくて… つまりは生菓子に対して乾いた菓子という事になります。 干菓子の中には「打ち物」「押し物」「寒氷」「琥珀糖(つや干金玉)」「雲平」「有平糖」や「煎餅」などが当たるかな、と思います。 代表格はやはり「打ち物」…一般的には「落雁」と呼ばれるものですね。
「落雁」の名の由来は表面に散らした黒胡麻を雁が降りてくる様に見立てたという説が有力なようです。 元々は保存や携帯用に穀物の粉を押し固めて作ったもので、竹筒や木片で単純に丸や四角に作られたとあります。 今にみる木型の登場は江戸時代の元禄年間で、江戸の後期文化文政頃には徳川家をはじめ各大名好みの落雁が各地で作られ、菓子職人はもちろん木型職人も腕を競ったようです。
落雁も時代と共に変化します。 明治維新の後は財閥や旧華族、あるいは神社仏閣でも「紋菓」として慶事、弔事、祭祀などの諸行事の折に用いられます。 戦後も家紋や寺社紋、会社のマークなどを象ったものが作られ、式典や記念品として配られたようですが、昭和40年代から次第に姿を消していきました。 これらに対して庶民の間に広がった「落雁」は、みやげ物や保存食として各地の風土に合わせて麦や穀物の粉、黒糖、胡麻などを使った素朴な物が多く、どこか鄙びた味わいがありますね。 茶席では有平糖と合わせて使われる事が多く、木型の豊富なデザインによって季節を表現してくれる楽しくも美しいお菓子です。
作り方の配合は種々ありますが、和三盆糖や葛粉を使った上品な味わいのものが好まれるよう思います。 混ぜる糖質、水分量、粉の種類によって食感は様々です。 それらの配合次第で固い、もろい、しっとり… 甘さや香りも異なります。 「砂を噛むようだ」とか「口のなかでボソボソする」とか嫌う方も多いですが、保存も利き、穀類と甘さを上手に組み合わせた愛しいお菓子だと思います。
現在では古い木型を買い求めオブジェとして飾ったり、また実際に使う為に骨董市などで掘り出し物を探される方も多いようですが、注意しなければならないのは、こうした市には使い古して細かい部分がシャープに出ない物が多々あります。 使い込んだ木型は再度、掘り直してもらって使うのだそうです。


実は「和菓子の本」を出すお話を頂いた折に、鹿沼市にいらっしゃる木型職人さんのお宅を訪ね取材をさせて頂いた事があります。 当時、全国に6人しかいないとのことでした。 鹿沼市といえばお隣は日光です。 日光東照宮の宮大工さんの子孫が鹿沼の地で家具職人さんとなり、さらに彫り物師としての木型を始められたとの興味深いお話を伺いました。
ちょうどその折、急な作品の依頼があり全工程を見せて頂くことができました。 判と同様に左右、凸凹が実際のものとは逆さまになります。 が、先生にはその計算がちゃんとできていて… 高低も深さも測ることなく感覚だけで掘り進められるのには驚きました。 そして出来上がったものはお見事! 全て同じ形、大きさ、深さで狂いはありませんでした。 スゴイ職人技です。 早速に私も我が家の家紋でもある桜を注文し作って頂きました。 あと、雛菓子向けの小さな貝や二重の観世水… お安くして頂いて…つい調子に乗って3点も買っちゃいました!(笑) こうした木型はやはり高価で、一般のお宅には必要ない物です。 教室では手軽に色々楽しめるようにと陶器の型を使います。 シャープさに欠けますし一つ一つなので手間は大変ですが、ご家庭で楽しむには十分かと思います。