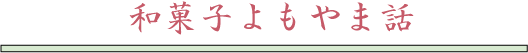
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2010年 2月 下萌え
二月を代表する「銘」に『下萌え』があります。 「したもえ?」はじめて聞く生徒さんは必ず首をかしげます。 「『雪間の草』でもいいのですが… 雪の下でわずかに萌え出る若草の事です」と説明すると、皆さんとても嬉しそうな顔をして「ああ…」とうなづかれます。 アスファルトで固められてしまった都会では、確かに死語ですね。 説明しないといけないような「銘」は困ったものだ!と思いつつ… この『下萌え』という 「銘」が大好きです。
溶けはじめた雪の下では、やがて迎える春の準備が着々と進行していて、それを見逃さない先人達の細やかな観察力とその表現力は素晴らしいと思います。 立春を迎える二月、本当は一番冷え込む時期ですが日に日に柔らかくなる陽ざしを見ながら「春待月」を楽しんだのですね。
和菓子には様々な種類のお菓子に写された『下萌え』の姿があります。 和菓子の銘の面白いところでもありますが、『下萌え』を表現する手法は色々です。 つまり、薯蕷で作る『下萌え』もあれば、きんとんや外郎で作る『下萌え』もあるのです。 私はよく道明寺で作ります。 中心になる漉し餡は土、淡い若草色に染めた道明寺が萌え出でた新芽、周りの氷餅がもちろん雪です。 聞けば写実的ですが真丸いお菓子は可愛くて… 「春、待つ」イメージに繋がるか ?と思っています。 また、茶巾絞りで作ることもあります。 こちらは緑色の出し方が微妙で… 逆に難しいと感じています。 白い生地に斑点のように薄緑を出すからには『“下”萌え』ではなく『雪“間”の草』の方がいいかな?とも思っています。 どちらも同じ ことで、どうでも良いようですが…(苦笑)



とても斬新で洒落ているなと思ったのは京都の末富さんの『下萌え』です。 薯蕷皮にポツンと開いた穴から緑の餡が覗いています。 末富さんは「桜重ね」や「紅葉重ね」など、こうしたサンドウィッチ状の薯蕷皮のお菓子をたくさん手がけておられますが、この『下萌え』には参りました! って感じでした。
何度も書いていますが、銘と、その表現の面白さは和菓子特有のものかも知れません。 「銘の楽しみ&楽しさ」は、日本文化が五感で楽しむ…と言われる所以で すね。 するどい観察力と洒落っ気、遊び心が必要だと、いつも感心します。。。(笑)