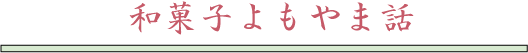
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2009年 8月 葛焼き
「葛焼き」というお菓子をご存知ですか。 おそらくは京都特有のお菓子であることや、注文によって作られる事が多い為、お茶に関わっておられる方や余程の和菓子好きでもない限り、なかなか口にする機会 は少ないのではないでしょうか。
 葛粉と砂糖と水そこに
小豆のこし餡を加えて漉し、鍋で練ってから冷やし固め、切り出したものに上新粉をまぶして鉄板で焼いたお菓子です。 冷やして頂く事が多いため、一般的には夏のお菓子とされていますが、私は一年中楽しめるお菓子として作っています。 たとえば冬にはこし餡ではなく白餡を使って真っ白に仕上げ「冬籠り」と銘をつけ、焼きたての熱々をお出しします。 また初夏には全く餡を入れずに葛粉だけで淡い水色に作り「五月雨」と銘をつけます。 他の和菓子同様に色や形の変化によって色々楽しめるお菓子です。
葛粉と砂糖と水そこに
小豆のこし餡を加えて漉し、鍋で練ってから冷やし固め、切り出したものに上新粉をまぶして鉄板で焼いたお菓子です。 冷やして頂く事が多いため、一般的には夏のお菓子とされていますが、私は一年中楽しめるお菓子として作っています。 たとえば冬にはこし餡ではなく白餡を使って真っ白に仕上げ「冬籠り」と銘をつけ、焼きたての熱々をお出しします。 また初夏には全く餡を入れずに葛粉だけで淡い水色に作り「五月雨」と銘をつけます。 他の和菓子同様に色や形の変化によって色々楽しめるお菓子です。
私も初めてこの「葛焼き」を頂いた時には「羊羹でもなく、外郎でもなく、葛餅でもなく… この優しい口当たりは何なのだろう」と、その不思議な食感 と優しい口当たりに感激しました。 また、その時までは冷やして頂くお菓子という認識しかありませんでしたが、嵐山の吉兆さんのお茶会で出された「葛焼き」が温かく… その美味しさに友人たちと驚いていると「当店では焼き立てをお出ししています」と平然と言われました。 茶会から戻って師匠に報告すると「お茶事なら当たり前でしょう」と一笑され、友人たちと落ち込んだ思い出があります。 確かに焼きたての温かい「葛焼き」も一興です。
この他にも「葛焼き」には沢山の思い出があります。 学園卒業後20年の節目に、同窓会での掛釜が巡って来ます。 例年3月にある同窓会は我々の時は6月に開催されました。 お菓子は「葛焼き」に決まり注文した先は末富さんでした。 何度も試作を繰り返して下さり… 結局「白(無色)、黄色、水色、紅色、緑色」の5色を水玉のように混ぜたものに決まりました。 あのように5色がきれいな丸を作り、どこにも気泡も入ること無く完成するのか、私には未だに謎のままです。(写真をお見せしたくて… 随分探しましたが見つかりません! 残念です!!)
また横浜のK先生のご依頼で三敬園のお茶会で使うお菓子を作らせていただく有難い機会を得ました。 依頼の趣旨は「同じもので四季を表現できるもの、お干菓子かそれに近い軽い感じのもので、春夏秋冬の4種で各100個」との事でした。 色や形を変え季節を表現するのは私が常に唱え最も得意としている事です。 「押しもの」や「寒氷」などの干菓子、冷凍のできる「こなし」など数種類の見本をお送りし、先生が選ばれたのが「葛焼き」だったのです。 私が一番選んで欲しくなかった(苦笑)ものです。 1個の「葛焼き」を仕上げるのに6面焼かなければなりません。 6面×400個で単純に2400面です。 当然、焼き上げは1回で完成とはなりませんので2400の倍か、3倍か… 転がして焼かねばなりません。(笑) 葛は当日勝負です! 冷凍のできるお菓子や干菓子のように作り溜めが出来ません。 もう、泣きそうでしたね! その茶会は面白いご趣向で、大広間に4箇所の席を作り同時に茶箱の点前をスタートさせるといった ものでした。 茶箱には「雪月花と卯の花」つまり冬・秋・春・夏の季節になぞらえたお点前があります。 白、黄色、桜色、若草色に仕上げた「葛焼き」が同時に運ばれて行く姿をこの目で見て みたかったです。
 この夏「我ながら…コレは!」と思う「葛焼き」が出来ました。 先月、山形のMちゃんから「葛焼きを送ってほしい。 餡の入ったのは水色で、餡の無い方はお任せ〜」との注文がありました。 この「お任せ」が一番困るんですねぇ〜(笑) 水色は餡入りの方に使ってしまいますし、ホタルや緑のイメージはもう遅いです。 夕焼けの空を見ていて思いつき、紫と白でマーブル状に作った中に金粉を埋めて「東雲」の銘を付けて送りました。 「素敵なお菓子をありがとう」とお電話を頂きひと安心です。 京都のMさんや東京のSさんにも時折こうした宿題を出されます。 こうした宿題の解決に向けて色々悩み、お菓子作りの難しさや楽しさを勉強させてもらっています。
この夏「我ながら…コレは!」と思う「葛焼き」が出来ました。 先月、山形のMちゃんから「葛焼きを送ってほしい。 餡の入ったのは水色で、餡の無い方はお任せ〜」との注文がありました。 この「お任せ」が一番困るんですねぇ〜(笑) 水色は餡入りの方に使ってしまいますし、ホタルや緑のイメージはもう遅いです。 夕焼けの空を見ていて思いつき、紫と白でマーブル状に作った中に金粉を埋めて「東雲」の銘を付けて送りました。 「素敵なお菓子をありがとう」とお電話を頂きひと安心です。 京都のMさんや東京のSさんにも時折こうした宿題を出されます。 こうした宿題の解決に向けて色々悩み、お菓子作りの難しさや楽しさを勉強させてもらっています。
思えば「葛焼き」とはずいぶん手間のかかるお菓子です。 練って蒸して、冷やし固め… 切りだして粉を付けて焼き、また冷やして… 教室ではデモンストレーション中に焼き立てをその場でお出しし、後の試食で冷やしたものを召し上がっていただきます。 どちらも好評です。 美味しいものには手が掛るという事ですね!