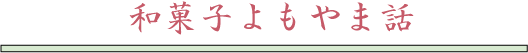
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や12年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2008年 5月 粽
5月5日は端午の節句、古くは薬草を摘み、蓬や菖蒲を門にかけたり、軒の上に上げて邪気を払い、病魔を避ける行事であったものが、菖蒲が尚武に通じることから、男子の成長を願う節句となり、さらには「子供の日」の祝日となったとされています。 が、最近ではゴールデンウィークとして大型連休の中に埋もれてしまって、残念ながら「子供の日」であることさえも、忘れ去られているように感じます。
♪ちまき 食べ食べ兄さんが〜♪ と童謡の歌詞にもあるように、端午の節句のお菓子は本来「粽」だと思います。 が、もう随分前から「柏餅」がこの日の、あるいはこの月のお菓子と、言わんばかりに店頭にたくさん並んでいますね。 今では「粽」よりも「柏餅」を求められるお宅が、圧倒的に多いことと思います。
「粽」と「柏餅」については、先月と同じ“関西”と“関東”の風習や文化の違いになるかと思います。 つまり、長く都があったために宮中行事の影響を強く受ける“関西”は「粽」で、武家社会の風習を重んじる“関東”は「柏餅」です。 柏の葉は新しい葉が芽吹くまで古い葉が落ちないことから『家を絶やさない』に通じ、男の子の節句である端午の節句のお菓子に用いられるようになったのだそうです。 「柏餅」の出現は江戸時代とされ、その歴史は当然「粽」より浅い訳です。
 「粽」の語源は茅(ちがや)の葉で包んでいたことから「茅巻き」が転じて「粽」になったとされています。 現在の笹の葉の姿になったのは、1月にお話しした川端道喜さんの初代が茅の葉に換えて、鞍馬山の笹の葉を使ったのが始まりだと言われます。 道喜さんの屋号が《御ちまき司 川端道喜》と名乗っておられるのは、その所以だそうです。
「粽」の語源は茅(ちがや)の葉で包んでいたことから「茅巻き」が転じて「粽」になったとされています。 現在の笹の葉の姿になったのは、1月にお話しした川端道喜さんの初代が茅の葉に換えて、鞍馬山の笹の葉を使ったのが始まりだと言われます。 道喜さんの屋号が《御ちまき司 川端道喜》と名乗っておられるのは、その所以だそうです。
「粽」の起源とされる屈原(楚の時代の詩人)の伝説は非常に面白い。 面白がってはいけない… 興味深いものです。
屈原は、愛国心から国の将来に絶望し、国を憂いて、汨羅江(べきらこう)に石を抱えて投身自殺をする。 その事を哀れんだ人々が、命日の5月5日に供物として、また亡骸が魚に食べられないようにと
の思いから竹筒に米を入れて投じ、その霊を祀った。 その後、漢の時代に歐回という人が三閭太夫と名乗る屈原の幽霊に出会い、「せっかく祀られる筒米も、蛟竜(こうりゅう=悪竜)に盗まれてしまう。 これからは楝樹(れんじゅ)の葉に包み、5色の糸で縛って欲しい」と告げ
られ、人々はそのお告げに従い、供物は無事に屈原の元に届くようになった。 これが「粽」の起源です。
この5色の糸が「鯉のぼり」の吹き流しの色になったとも言われています。 そういえば、帯締めにも5色の細い紐を束にした厄除けのものがありますね。 因みに「鯉のぼり」は“鯉が竜門の滝を登れば、龍となって天を駆ける”という故事に基づくものだそうです。
和菓子の世界には、こうした中国の故事や伝説に由来する行事、それに伴う「お供え」や「邪気を祓う」という意味を持つお菓子が非常にたくさん登場します。 日本に伝来し「厄除け」や「疫病除け」または「子孫繁栄」 などと、その意味合いが広がって行くのも面白いと思います。
「粽」は端午の節句の他にも祇園祭りに代表されるように各地の夏のお祭りの供物として、作られることも多いようです。 また鹿児島の「あくまき」や新潟の「灰汁笹巻き」などには、粽の原型とも言える興味深いものがあります。