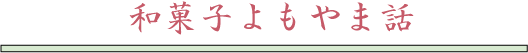
和菓子のお教室をはじめさせて頂いて早や13年になります。
たくさんの美味しいお菓子、珍しいお菓子に出会いました。
そんなお菓子の思い出やエピソードを、少し… お話したいと思います。
◆ 2011年 3月 糊こぼし
関西に春を呼ぶ行事に奈良、東大寺二月堂のお水取りがあります。 近くに居ながら… 修二会の期間中(3月1日〜14日)連日行われているという荘厳な火の舞「お松明 (たいまつ)」を、一度も見に行った事がありません。 “春を告げる行事”と、されながら… 一方では「お水取り(3月12日)の頃が一番寒い」とも言われています。 関西では「お水取りが済むまでは寒いですねぇ〜」が、この月の挨拶でもあり、お水取りが終わると、やがて《暑さ寒さも彼岸まで》… 春の彼岸を迎えます。 いよいよ、待ち望んだ春ですね。
修二会で思い出すのは、何といっても萬々堂通則さんの「糊こぼし」です。 子供の頃に父のお茶(茶道)仲間の先生からこのお菓子を初めて頂いた時、京菓子を見慣れていた私には、子供心にも“どぎつい色”が何とも受け入れ難いものでした。 が、口にすれば… 大好きな黄味餡とこなしです。 きっと、その時… 大いに嬉しい顔をしたに違いありません。(笑)


「糊こぼし」とは東大寺開山堂の庭に咲く名椿「良弁椿」の別名です。 修二会の行法中、開山良弁僧正の名前を頂いた椿を模して和紙で造花を作り、それを二月堂内の柱に供花 (くげ)として飾るそうです。 「良弁椿」には、その造花を作る際に糊をこぼしたような斑点があることから、「糊こぼし」の名がついたのだそうです。 そして造花の「糊こぼし」をモチーフにして出来たのが、お菓子の「糊こぼし」という事ですね。
このお菓子の由来を知りあの色と形に納得できたのは、随分おとなになってからのことでした。 奈良にはこの季節限定で、他店でも「開山椿」とか「御堂椿」の名で同じようなデザインのお菓子がありますが、私はやはり… 椿のかわいい外箱を妹と取りあった… ずばり「糊こぼし」が一番印象深い“椿”のお菓子です。